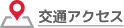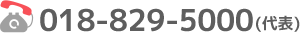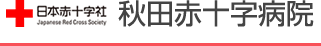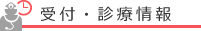婦人科
診療科紹介
婦⼈科では良性疾患から悪性疾患、感染症、生殖医学、⼥性医学まで幅広い分野に対応しています。特に⼦宮頸がん、⼦宮体がん、卵巣がんなど婦⼈科悪性腫瘍に関しては、婦⼈科腫瘍専⾨医が細胞診専⾨医でもあり、診断から治療までの⼀貫した診療を行っています。また、⼦宮筋腫、卵巣嚢腫、⼦宮内膜ポリープなどの良性疾患では、腹腔鏡技術認定医のもと、腹腔鏡や⼦宮鏡による内視鏡下⼿術を積極的に取り⼊れています。2024年10月より子宮体がんの腹腔鏡手術を導入しました。生殖医学に関しては、一般不妊症検査は施行可能です。必要に応じて、体外受精や顕微授精等を施行可能な専門施設への紹介を行っております。
基本方針
当科が⽬指す医療は、多くの経験に基づいた質の⾼い医療と、患者さんご⾃⾝が納得し、選択し、満⾜できる医療です。当科では、丁寧な説明を行っております。良性疾患はもちろんのこと、たとえその病気ががんであっても、最終⽬標は社会復帰です。それは、病気になる前の⽣活に戻ることを意味しています。仕事をしている⽅は、仕事に復帰することです。そして、治療期間中の⽣活の質(QOL)が保障されることもきわめて重要なことです。
特徴・特色
悪性疾患に関しては、診断から⼿術、術後の治療まで、すべてを当院で⾏います。エビデンス(証拠)に基づく、治療ガイドラインに沿った医療を基本としながら、患者さんの希望や、年齢・合併症・病状を考慮した最善の医療を提供します。また、外科、放射線科、外来化学療法室、緩和ケア内科、がん相談⽀援センターなどとのタイアップにより集学的医療を⾏います。リンパ節郭清術後の下肢リンパ浮腫予防のため、⼊院中よりセルフケアの指導を⾏い、退院後もがん相談⽀援センターのリンパ浮腫相談窓⼝を通じ、指導を継続しています。腹腔鏡、子宮鏡などの低侵襲手術(傷あとの目立たない手術)により、身体への負担を少なく、より早期の社会復帰ができる医療を提供します。当科受診をご希望の場合は、かかりつけ医に相談の上、当院の地域医療連携室を通じて予約をお取り下さい。
地域医療連携室
TEL 018-829-5233(直通) FAX 018-829-5222(直通)
主な対象疾患と治療内容
- 子宮頸部異形成、子宮頸がん
子宮頸部前がん病変である高度異形成には子宮頸部円錐切除術を取り入れています。進⾏⼦宮頸がんに対しては、⾻盤神経温存広汎⼦宮全摘術または同時化学放射線療法を標準とし、初期の⼤量性器出⾎のコントロールには⼦宮動脈塞栓療法を⾏っています。 - 子宮体がん
局所進⾏⼦宮体がんに対しては、⼦宮全摘術に加え、必要に応じ⾻盤・傍⼤動脈リンパ節郭清術や大網切除術を⾏っています。再発リスクの⾼い患者さんに対しては、パクリタキセル、カルボプラチンによる術後補助化学療法を施⾏しています。また、再発⼦宮体がんに対しては、2021年12⽉に保険適応となったレンバチニブ、ペムブロリズマブの併⽤化学療法を開始しています。2024年10月より腹腔鏡下子宮体がん根治手術の施設認定を取得し、早期子宮体がんに対し腹腔鏡下手術を行っています。 - 卵巣がん
卵巣がんは進⾏がんに対して、初回⼿術で可能な限りの腫瘍減量⼿術を⾏います。完全切除が可能な場合は、消化器外科と協⼒し、直腸合併切除や腸管切除を⾏うこともあります。切除困難の場合には審査腹腔鏡を行い、早期に術前化学療法を開始できる体制をとっています。卵巣腫瘍の場合、術前に診断や組織型の推定が難しい場合が多いため、病理診断科と協力し術中迅速組織診断や細胞診断を積極的に⾏っています。また、ゲノム医療の普及に伴い、MyChoice検査やMSI検査を導入しています。進行卵巣がんや再発卵巣がんに対する維持療法としてPRAP阻害剤もすでに導⼊しています。当院は、2021年に遺伝診療センターを開設し、BRCA遺伝⼦変異保持者の卵巣癌/卵管癌に対するリスク低減卵管卵巣摘出術(RRSO)の施設認定を取得し、乳腺外科との同時⼿術にも対応しています。 - 子宮筋腫
⼦宮筋腫に対しては、ライフステージ、症状、⽣活スタイルに合わせ、薬物療法や⼿術療法を提供しています。薬物療法には⼥性ホルモンの分泌を抑えることにより筋腫の縮⼩を期待する偽閉経療法があります。⼀⽅、⼦宮筋腫が⼤きく、過多⽉経などの症状が強い場合は⼿術治療を⾏なっています。⼦宮筋腫を⼿術で治療する場合、①⼦宮を全摘する⽅法、②⼦宮筋腫のみを摘出する⽅法(筋腫核出術)があります。当科では腹腔鏡や⼦宮鏡といった内視鏡下での⼿術を積極的に取り⼊れています。侵襲の少ない⼿術を提供するために、①⼦宮全摘の場合には、腹腔鏡⼿術で、②筋腫核出の場合には腹腔鏡⼿術または⼦宮鏡下⼿術で⾏うことが可能かどうかを⼗分に検討したうえで⼿術⽅法を決定します。 - 子宮内膜症
⼦宮内膜症は、⼦宮内膜が⼦宮内腔以外の場所(卵巣、⼦宮筋層内、腹膜など)に発⽣することで起きる疾患で、お腹の中で炎症や癒着を引き起こし、⽉経困難や性交痛、排便痛、不妊などの原因となります。卵巣に⽣じた⼦宮内膜症は卵巣⼦宮内膜症性嚢胞、別名:チョコレート嚢胞と呼ばれています(古くなった⾎液がチョコレート様にみえるため)。チョコ レート嚢胞は0.5〜1%と頻度は⾼くありませんが、がん化のリスクもあり定期的な経過観察が必要です。治療法は⼤きく分けて、薬物療法と⼿術療法があります。症状や年齢、挙児希望の有無などに応じて、相談をしながら⽅針を決定していきます。
薬物療法:薬物療法には、主に痛みをおさえるための対症療法と、⼦宮内膜症の進⾏を抑えたり、病巣を⼩さくさせるホルモン療法があります。
⼿術療法:腹腔鏡⼿術を⾏っています。年齢や挙児希望によって、嚢胞核出か付属器(卵巣+卵管)摘出を選択しています。術後の再発予防のために、ホルモン療法を⾏うこともあります。 - 月経前症候群・月経困難症
強い⽣理痛や⽣理前にはじまる体調不良は、ぜひ⼀度婦⼈科を受診してください。⽉経前症候群や⽉経困難症は、⽉経時期の⼥性ホルモンの変化に伴う疾患です。症状には個⼈差がありますが、⽉経の頃からはじまる強い下腹部痛や頭痛、腹部膨満感、吐き気、頭痛、疲労感、脱⼒感、⾷欲不振、イライラ、下痢、うつ症状などが代表的です。⼥性ホルモンによって引き起こされる市販の痛み⽌め薬では効かない⼦宮収縮痛や諸症状であっても、ジエノゲストや低⽤量ピルなどの薬物療法が有効です。漢⽅薬も併⽤できます。⼿術による病変除去が⽉経痛の治療に有効な場合もあります。当院では器質性⽉経困難症に対する適正なホルモン療法などに係る研修を受講した医師が、患者さんごとに適切な治療計画を作成し、継続的な医学的管理を⾏っています。 - 良性卵巣腫瘍
卵巣腫瘍には嚢胞性と充実性があり、良性の嚢胞性卵巣腫瘍のことを卵巣嚢腫(嚢胞)と呼びます。卵巣腫瘍は、無症状の場合が多く、検診などで偶然⾒つかることがあります。卵巣腫瘍の⼤きさや性状により、⼿術療法を考慮します。良性腫瘍が推定されれば腹腔鏡⼿術を行います。嚢胞性の場合、①腫瘍を含めて卵巣と卵管を摘出する⽅法(付属器摘出)と、②卵巣の正常部分を温存する⽅法(嚢胞核出術)があります。どちらの術式を選択するかは年齢、腫瘍の⼤きさなどを総合的に判断して決定します。⼀⽅、充実性腫瘍は付属器摘出が⼀般的です。
診療実績
2024年度の全⼿術に占める内視鏡⼿術の割合は65%であり、前年度に比較し20%以上増えています。悪性腫瘍⼿術は28件で、全⼿術の15%でした。⼦宮頸がんに⽐べ、⼦宮体がん・卵巣がんが多いのが当科の特徴です。進⾏⼦宮頸がんに対しては⼿術ではなく、同時化学放射線療法を⾏うこともあります。⼦宮付属器⼿術は近年、開腹⼿術から腹腔鏡⼿術に⼤きくシフトし、今後もこの流れが継続するものと考えられます。⼦宮頸部異形成に対する⼦宮頸部円錐切除術は23件です。(表1、2)
表1.手術内訳
| 手術名 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開腹手術 | 85 | 85 | 67 | 71 | 30 |
| 悪性腫瘍手術 | 38 | 42 | 38 | 27 | 22 |
| 子宮全摘出 | 34 | 31 | 23 | 27 | 6 |
| 付属器手術 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1 |
| 子宮筋腫核出術 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 膣式手術 | 69 | 29 | 32 | 37 | 35 |
| 円錐切除術 | 57 | 25 | 26 | 28 | 23 |
| 子宮全摘術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子宮脱手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流産手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| その他 | 12 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 腹腔鏡手術 | 87 | 72 | 95 | 72 | 100 |
| 悪性腫瘍手術 | 6 | ||||
| 子宮全摘術 | 21 | 9 | 24 | 22 | 34 |
| 付属器手術 | 55 | 52 | 55 | 40 | 50 |
| 筋腫核出術 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 |
| 子宮外妊娠手術 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| その他 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 子宮鏡手術 | 6 | 12 | 13 | 11 | 19 |
| 合計 | 247 | 198 | 207 | 191 | 184 |
表2.悪性疾患手術件数(円錐切除術を除く)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子宮頸がん | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 子宮体がん | 15 | 19 | 15 | 13 | 19 |
| 卵巣がん | 17 | 21 | 21 | 14 | 9 |
| その他 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 38 | 42 | 38 | 27 | 28 |
2024年度の年間化学療法患者数は48人で、入院・外来化学療法患者の延べ人数はそれぞれ223人、114人でした。(表3、4)
これには、外来でのオラパリブなどによる抗がん剤内服維持療法が含まれていないため、実際の抗がん剤使用人数はもう少し多いと考えられます。
表3.化学療法患者数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 64 | 69 | 78 | 61 | 48 |
表4.化学療法延人数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 279 | 317 | 263 | 165 | 223 |
| 外来 | 145 | 137 | 104 | 84 | 114 |
今後の目標
婦人科悪性腫瘍の治療分野では、標準治療が急速に変化していくなかで、常に最新の情報を入手し、治療に取り入れてゆくことが目標です。また、患者さんのQOL向上のため、入院期間の短縮、外来化学療法、緩和ケア、術後リンパ浮腫相談・施術などに、さらに多くの改善を心掛けたいと思います。一方、内視鏡手術に関しては、今後さらに外来を充実し、適応疾患を拡大して手術の必要な患者さんに対応していく予定です。
婦人科関連研修施設認定
- 日本専門医機構産科婦人科領域専門研修プログラム連携施設
- 日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設
- 日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設
- 日本女性医学学会専門医制度認定研修施設
- 日本臨床細胞学会教育研修施設認定
担当医の紹介
| 役職名等 | 氏名 | 資格等 |
|---|---|---|
| 婦人科部長 | 大山 則昭 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医・指導医 日本臨床細胞学会細胞診専門医・教育研修指導医 日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医・指導医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本産婦人科乳腺医学会乳房疾患認定医 日本がん治療認定医機構暫定教育医 日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医・指導医 東北ブロック医師臨床研修指導医 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了 医学博士 |
| 婦人科副部長 | 富樫 嘉津恵 | 日本専門医機構認定産婦人科専門医 日本生殖医学会生殖医療専門医 日本産科婦人科学会産婦人科指導医 日本周産期・新生児医学会周産期専門医(母体・胎児) 日本産科婦人科内視鏡学会腹腔鏡技術認定医 日本内視鏡外科学会技術認定証(産科婦人科) 日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース(Aコース)インストラクター 臨床研修指導医 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了 |
| 婦人科副部長 | 東海林 なつみ | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了 |
| 医師 | 福岡 日向 | がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了 |
外来診察表はこちらをクリックしてください